病気解説
循環器内科
慢性心不全
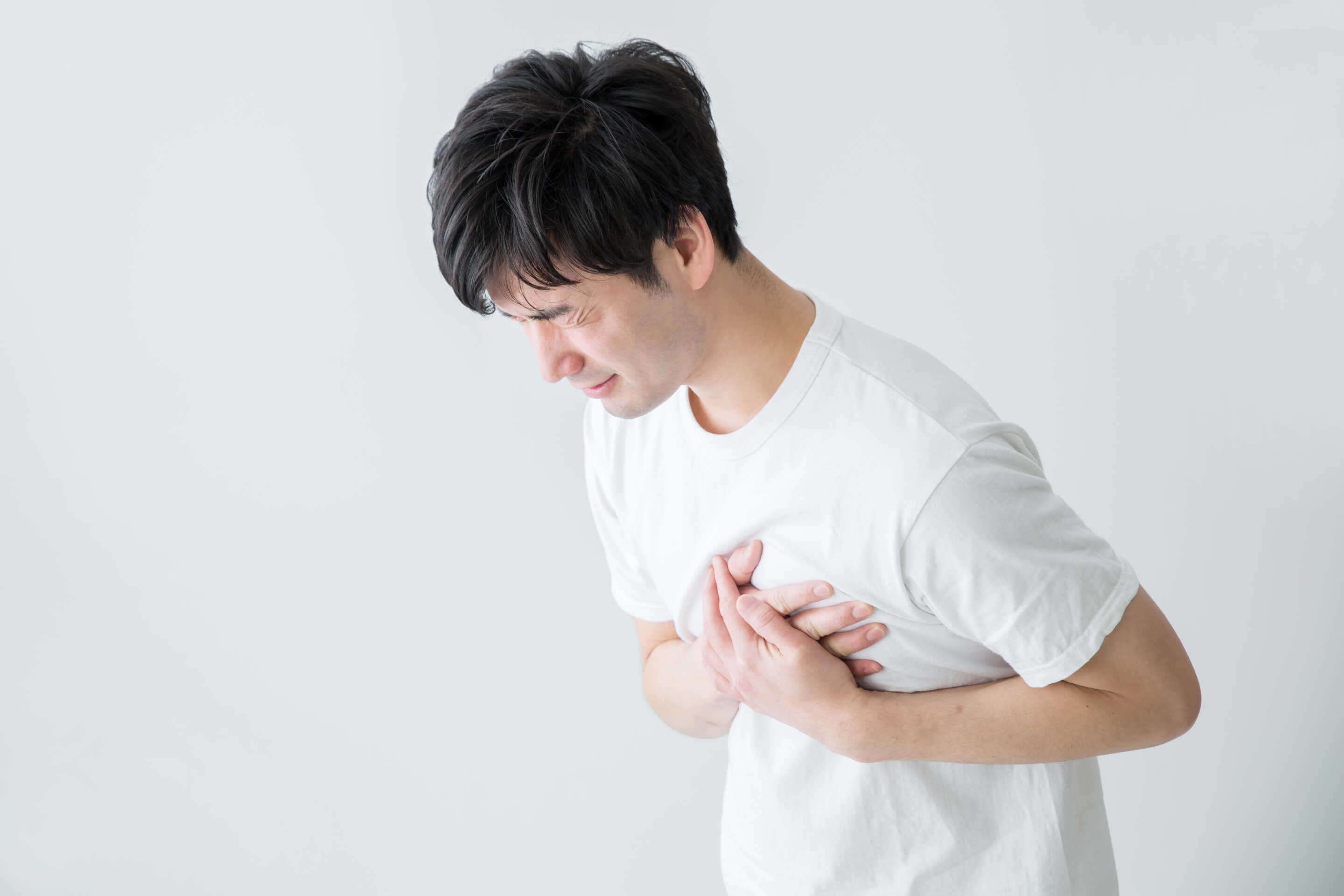
慢性心不全は、気づかないうちに進行している病気で、気づいたときには手に負えなくなってしまう恐れがあります。
正しい知識を持って対処をしないといけない病気である上に、長く付き合う必要があります。
もし、身体に異変を感じた場合は、必ず病院に行き、適切な診察・治療を受けるようにしましょう。ふじた医院へのアクセスはこちら。
心不全とは
心臓は全身に血液を送り出すポンプのような働きをしています。
何らかの原因によりこのポンプの働きが弱まり、全身に十分な血液を送り出せなくなってしまった状態のことを心不全といいます。
心不全は、症状が進行するスピードの違いから急性心不全と慢性心不全に分けられます。
急性心不全
急性心不全は突如発症し、急速に症状が進行します。慢性心不全
心臓に負担がかかり続けることで徐々に症状が進行します。
慢性心不全が急激に悪化することで急性心不全となることもあります。
慢性心不全の症状
慢性心不全は、初期と後期で症状に違いがあります。
心不全は気づきにくい病気であるため、時期によって症状にどのような違いがあるかは理解しておかなければなりません。
慢性心不全の初期症状
慢性心不全の初期症状は血液量が低下するために、少しの動作でも疲れと動悸が表れ、手足の冷えを感じ、夜間の多尿といった症状が出ます。
年齢、風邪、過労・貧血・喫煙の影響などと勘違いすることがあり、心不全だとは気づきにくい症状です。
慢性心不全の後期症状
慢性心不全の後期症状は、咳・痰・呼吸困難・下肢のむくみ・急な体重増加・尿量の減少・倦怠感や食欲不振・腹部膨満感などの症状が出ます。
痰は白っぽい泡のようで、呼吸困難は坂道や階段など負荷がかかったときや仰向けで寝たときに起こります。
むくみは夕方強くなり、靴がきつくなったり、顔がパンパンになったりすることで気づくでしょう。これは、余分な水分を体外へ排出できず、肺に過剰な水分が回ってしまうために起こります。
全身から心臓に血液が戻りにくいため、横になると息苦しくなり、身体を起こすと少し楽になります。
さらに、腸や胃にもむくみが出て、倦怠感や食欲不振・腹部膨満感症状が出ます。
ここまで、慢性心不全の症状が出ると危険なので、すぐに病院を受診しましょう。
慢性心不全は徐々に進行しますが、心拍出量を維持しようとするさまざまな代償機構が働くため、しばらく症状が出ません。
そのため、一般に症状が現われたときには、かなり悪化した状態となります。
慢性心不全が重症化すると、経過中に何度も急性心不全の発症を起こし、その都度入退院を繰り返すようになるケースが多くみられます。
ふじた医院での検査と治療
ふじた医院でも慢性心不全の検査を行っております。ふじた医院へのアクセスはこちら。
ふじた医院では以下の検査方法を採用しております。
心電図検査
不整脈と古い心筋梗塞の有無を調べます。
BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)
BNPは心不全の状態が悪いときに数値が高くなるため、この値によって肝臓や腎臓の障害を確認します。
もし、慢性心不全であると診断された場合には薬剤治療を行っていきます。
- 利尿剤
- トルバブタン
- 降圧剤
その他の検査方法・治療法
その他の治療法が必要な場合は設備がある病院をご紹介しますので医師にご相談ください。
| 胸部レントゲン撮影 | 心臓の拡大や肺のうっ血 |
|---|---|
| 心エコー | 心臓の収縮機能と弁膜症の有無 |
| 血液検査 | BNPの値を確認 100pg/dl以上だと心疾患があると判断され、500pg/dl以上だと重症心不全と診断されます。 |
また、薬剤治療の他に以下のような治療法があります。
心臓カテーテル治療
入院治療が必要ですので、治療が必要と判断した患者さまは関連病院の筑波大学附属病院、つくばメディカルセンター病院へ紹介します。
外科的治療
弁膜症、大動脈瘤の患者さまは状況によって手術が必要です。
心臓リハビリテーション
心臓に過負担にならないよう、患者さまの状況に合わせて医師による診察と運動処方に合わせて、心電図モニターリングしながら心臓リハビリテーション指導士、理学療法士の立会の元で運動を行います。
心不全の原因
心不全は以下にあげる心疾患や、要因を原因として引きおこったり、悪化します。
心疾患
- 心筋梗塞
- 心筋炎
- 心臓弁膜症
- 先天性心疾患
- 高血圧
- 不整脈
- 肺高血圧症
その他要因となるもの
- 塩分の摂りすぎ
- 肥満
- 喫煙
- 加齢
- 脂質異常症
- 糖尿病
上記のものに注意して慢性心不全にかからないよう心がけましょう。
痛みが出たときの対処法
慢性心不全で痛みが出たときは、安静が大事なので、まずはベルトなどを外し、仰向けで寝ましょう。
外出先の場合は、壁など寄りかかれる所で坐位を保ちます。
医師から硝酸剤(錠剤)を処方されている場合は、舌の下に入れて唾液で溶かしましょう。 硝酸剤は、即効性があり、1~2分のうちに胸痛が落ち着きます。
5分経っても痛みが治まらない場合は、もう1錠使用します。ただし、1回の痛みで使えるのは2錠までです。 それ以上使うと低血圧となり、危険なので注意してください。
舌が少しピリピリする、頭痛がする、身体が火照る、軽い不快感が出ることがありますが、血流が良くなった証拠なので心配ありません。
慢性心不全の症状が出たときは、痛みが出た日時、何をしているとき、痛みの強さ、薬の効果などの記録をつけておきましょう。 慢性心不全による痛みが治まらない場合は、迷わず医療機関で受診してください。
気になる痛みや症状があったらお気軽にご相談ください
WEBでお問い合わせ