病気解説
内科
めまい
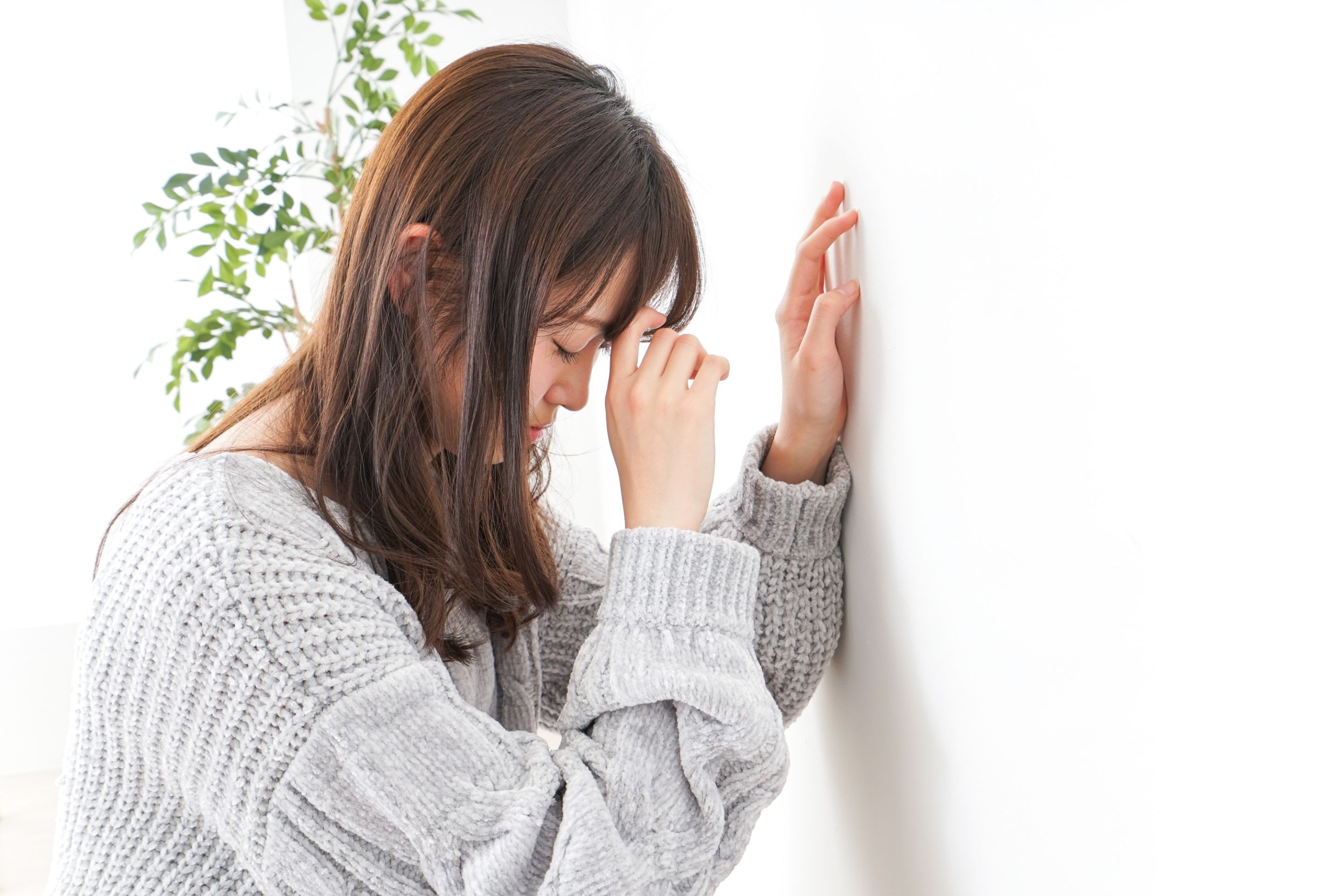
「景色がクルクル回る」
「なんかフワフワして気持ちが悪い」
そんなめまいに関する悩みを抱えている人は、結構多いと思います。
「熱があるわけでもないし、少し休めば自然と治るだろう」なんて軽く考えてしまいがちですが、めまいには重大な病気が隠れている場合もありますので、安易に放置せず長く続く場合には、早めに病院へ行き、適切な治療を受けてください。
ふじた医院のアクセスはこちら。
めまいが起きるしくみ
私たちは、目からの視覚情報と手足の筋肉からの知覚情報、内耳の三半規管からの平衡感覚を総合して脳が判断して自分の姿勢や運動を認識しています。
しかし、どれか一部の調子が悪くなり、感覚情報の間でズレが生じると脳で姿勢や運動がうまく処理できなくなり、「めまい」を起こします。
めまいは、回転性めまい、浮動性めまい、立ちくらみのようなめまいの3種類に分けられます。
回転性めまい
回転性めまいは、自分や周囲のもののどちらか、または両方がグルグルと回転しているように感じるめまいです。
回転性めまいの場合、めまいに伴って嘔気や嘔吐が出現することが多くあります。また、バランスが取りにくく歩くのが難しくなります。
眼振(周りから見て眼球が素早く揺れている)が見られることもあります。回転性めまいは、耳や脳の平衡感覚の維持に関する部位での異常が原因で多く発生します。
浮動性めまい
浮動性めまいは、身体がフワフワしてまっすぐ歩けなくなるように感じるめまいです。
回転性めまいとは違いグルグルという感覚はありません。めまいとともに頭痛や手足のしびれ、麻痺などを生じることがあります。浮動性めまいは脳の循環不全や心臓疾患によって起こることがあります。
立ちくらみのようなめまい
立ち上がったときに急にクラっとするめまいです。目の前が暗くなったり、失神したりすることもあります。
これは貧血や心臓疾患、心因性のめまいで起こることがあります。
動揺視
静止しているはずのものが、揺れて見えるタイプのめまいです。
主な原因疾患として、脳腫瘍(眼窩腫瘍)、心臓疾患などが挙げられます。
また、眼精疲労によって動揺視の症状が現れることもあります。
めまいを引き起こす病気
めまいが症状として表れる病気は、多岐にわたります。
良性発作性頭位めまい症
頭を勢いよく動かしたタイミングに発作的に短い時間(数分程度)のめまいを感じるもので、長時間のめまいはありません。
早朝寝返りを打った直後、勢いよく起きたときなどに起こりやすいと言われています。耳鳴りや難聴が起こることはありません。
ときには、眼球が小刻みに揺れる「眼振」を伴うこともあります。
メニエール病
メニエール病の三大症状が、「回転性のめまい」「耳鳴り」「難聴」です。突然周りがグルグルと回転しているように感じる激しいめまいがおき、立っていても寝ていても辛いほど平衡感覚が著しく崩れます。
このめまいと同じタイミングで、耳鳴りや耳が詰まった感じ、難聴(特に低音が聞こえにくい)といった症状が起こります。
一回の発作は30分から数時間に及ぶものもあり、この発作を幾度となく繰り返します。発作中は吐き気を伴い、頭が重くなり圧迫感を伴う頭痛も出現します。
脳卒中
脳の病気が原因でめまいが起こることはそれほど多くありませんが、もし起こってしまった場合は小脳など脳幹の出血や梗塞によるものです。
脳卒中が原因でめまいが起こった場合、ろれつが回らなくなる、意識障害を伴う、手足が動きにくくなるなどめまい以外のさまざまな症状が表れます。
めまいとともにこのような症状が認められた場合は速やかに医療機関を受診する必要があります。
脳梗塞
脳梗塞動脈硬化による血管の狭窄、血栓が生じたことなどで、脳の血管が詰まってしまう病気です。
めまいの他、身体の片側の麻痺、身体に力が入らない、ろれつが回らない、視力障害などの症状を伴います。
脳腫瘍
高血圧などに伴う動脈硬化を主な原因として、脳の血管が破れて出血している状態です。
めまいの他、強烈な頭痛、身体の片側の麻痺、吐き気や嘔吐、意識障害などの症状が見られます。
くも膜下出血
くも膜下出血脳動脈瘤の破裂を主な原因として、脳を包む「くも膜」で血管が破れて出血している状態です。
めまいの他、強烈な頭痛、吐き気・嘔吐、意識障害などの症状が見られます。
脳動脈瘤が破裂する前に治療を行うことで、くも膜下出血の予防になります。
めまいの予防法
めまいは一度起こってしまうと劇的に改善させる方法はないので、めまいを起こしにくい体質にすることが大切です。
ここで紹介する方法は、耳のなかの平衡感覚を感じる器官が原因となって起こるめまいに対する対処法です。
ストレスや神経の乱れ、血流不全が原因となって起こるめまいなどに対処するためには、規則正しい生活と栄養バランスのいい食事をしっかりと取ることが一番大切です。
めまいを予防するためには、平衡機能を鍛えることが有効と言われています。人間の平衡感覚を司るのは小脳と三半規管なので、この二つを重点的に鍛えましょう。
小脳のトレーニング
目を動かすと小脳を鍛えることができます。
利き手をまっすぐ前に伸ばし、親指を立てます。反対の手の人差し指を顎に当て頭を固定します。
伸ばした利き手を左右45度ずつゆっくり動かし、目でしっかりと親指の爪を追いかけます。
三半規管のトレーニング
小脳のトレーニング同様、利き手を伸ばして親指を立てた手を左右に動かし目で追いかけますが、顎の固定はせず首を動かします。
もし、スムーズに追いかけられないという方は三半規管の機能が低下している可能性があります。
その場で実践できる対処法
実際にめまいが起こった際にその場でできる対処法をいくつかご紹介いたします。
安静・水分摂取
めまいの種類にかかわらず、まずは安静にしてください。
立っていると転倒する可能性があるので、座るか、またできるならば横になってください。頭の位置を低くすることが大切です。
脱水を原因としてめまいが起こることもありますので、適量の水分を摂取してください。
目・耳に入る刺激を避ける
部屋を暗くしたり音楽を消すなどして、目に入る光、耳に入る音をできるだけ避けてください。
ツボを刺激する
もし、めまいが起こってしまったら、めまいに効果があるツボを刺激してみるのもいいでしょう。
強く刺激するのではなく、気持ちがいいと思える程度の力加減で深呼吸をしながら刺激していきます。
翳風(えいふう)
めまいの原因の一つである内耳の機能を高めるツボです。耳たぶの後ろ、耳下腺リンパ節の近くにあります。
きょういん
外耳の後ろ、ちょうど真ん中で、骨の内側にあるくぼみを指します。翳風の斜め後方にあります。
医療機関を受診する
上記を実践してもめまいが続く、一度治まったものの頻繁にめまいが繰り返されるという場合には、医療機関を受診してください。
場合によっては、命にかかわる原因疾患が隠れていることがあります。
女性特有のめまい
ここまでめまいに関して解説してきましたが、これらは男女どちらにも起こるめまいのケースです。
女性には、今まで記載してきためまいの他にも、女性特有のめまいを引き起こす原因が存在します。そのため、男性に比べてめまいで苦労する方が多いです。女性特有のめまいについて、詳しく解説していきます。
女性にめまいが多い原因
女性にめまいが多い原因として、男性も起こり得るめまいの原因に加えて、女性特有のPMS(月経前症候群)や月経困難症、更年期障害の症状としても現れることがあげられます。
特に更年期の女性は、閉経期前後の約10年間に卵胞ホルモンであるエストロゲンの分泌が急激に減少し、自律神経のバランスが乱れます。
それに加えて感覚器官の加齢変化によって、めまいや耳鳴りなどの症状が出やすくなります。
しかし、更年期のめまいの原因は、動脈硬化、高血圧、メニエール病、突発性難聴など重篤な病気が隠れている場合があるので、めまいが長く続くときは病院へ行きましょう。
予防方法
他のめまいと同様に食生活や生活リズムを見直すことが大切です。
めまいは血圧が低すぎても高すぎても起こります。また自律神経のバランスが崩れると、血圧が不安定になり、脳が血液不足になって立ちくらみやめまい、ふらつきが発生しやすくなるので、食事はバランスよく時間を決めて3回、塩分を控えて腹八分目にしましょう。
大豆食品やアーモンド、アボカド、かぼちゃなどは、血流を促し自律神経のバランスを整えるビタミンEを豊富に含んでいるのでおすすめです。また青魚類は血液をサラサラにしてくれるEPAやDHAを豊富に含み、血圧の安定が期待できます。
さらに食事だけでなく、ストレスをためない生活や質の良い睡眠も重要です。過労や心労などのストレスが引き金となりめまいが起こる場合もあるので、心配ごとを一人で溜め込まないようにしましょう。
なるべく毎日同じ時間に就寝・起床し、睡眠習慣を整え、ゆとりのある生活を心がけることもめまいの予防に繋がります。
急に立ち上がったときにめまいや立ちくらみを起こしてしまう起立性低血圧の場合は、ひざ下を適度に締め付けて上半身に血液が戻りやすくする着圧ソックスを履くと、血流の調整をサポートしてくれます。
また、ほかの更年期障害の症状がみられる場合には、女性ホルモンや漢方薬など更年期障害の治療をすることでめまいも改善することがあります。
病院での検査と治療
病院では以下のような検査を行います。
血液検査
まず、今起こっているめまいがなにか、重大な病気のサインではないかどうかを調べるため血液検査を行います。
また、血圧が高いことによってめまいを感じることもありますので、血圧も同時に測定します。
レントゲンなどの画像検査
めまいが起こる原因として、耳の病気や骨、筋肉に病気があることもあります。
そのため、首や頭周辺の骨の異常を否定するため、レントゲンを撮ることもあります。
さらに、脳梗塞や脳出血、脳腫瘍など脳の病気が原因で起こることもあるため、造影剤を使った脳血管の撮影を行ったり、CT撮影を行ったりすることもあります。
聴力検査
三半規管と音を聞くための蝸牛などの器官は密接に関連しているため、聴力検査を行い聴力に異常が起こってないかどうかを検査します。
平衡感覚の検査
めまいが起こっているときは、自分がまっすぐ歩いていると思っていてもフラフラしていることもあります。
また左右に揺れるのか、一方に偏っているのかを検査することがあります。
重心動揺検査
あまり聞きなれない検査ですが、めまいの診断を目的とした大切な検査です。
開眼時、閉眼時、それぞれまっすぐ立ったときの重心の動揺を分析し、平衡感覚の維持に関わる機能を調べます。
温度刺激検査
耳のなかに冷たい空気を入れ、そのときに起こるめまいを調べる簡単な検査です。
病院でのめまいの治療
基本的にめまいの治療は、抗めまい薬や、吐き気止めなどの内服薬を対症療法的に投与することで行います。
めまいの原因として精神的なものが考えられるようであれば精神安定剤や自律神経を調整する薬、循環不全が原因で起こっていると疑われる場合は血液循環を改善する薬を投与します。
良性発作性頭位めまい症などであれば、運動療法やリハビリ療法が行われることがあります。
めまいは、怪我のように見た目に分かりやすく異常がでてくるわけではなく、熱がでるなどの客観的に分かりやすい症状があるわけでもありません。
また、めまいは原因が分かりにくく、診断がつきにくいこともあり、「めまいが辛い」と言っても、「気の持ちようだ」、「緊張感が足りない」、「たるんでいる」などの精神論で片付けられがちです。
実際、医療機関を受診しても、めまいの専門ではない医師だった場合、「特に異常はありません」とあしらわれてしまうこともあるようです。
しかし、めまいはれっきとした病気の症状であり、病院を受診する人のなかで訴えの多い症状の一つです。
めまいにはさまざまな原因があり、重大な病気が潜んでいる可能性も考えられるため、素人判断は大変危険です。
早めに適切な医療機関を受診することで症状が緩和されて楽になったり、悪化する前に対処できたりすることもあります。
めまいを感じたら躊躇せず早めに適切な病院を受診するようにしましょう。
気になる痛みや症状があったらお気軽にご相談ください
WEBでお問い合わせ